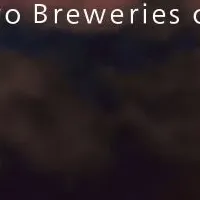

11月11日は鮭の日!サーモン寿司誕生40周年を振り返る
日本の食文化に欠かせない存在となったサーモン。11月11日は「鮭の日」として知られ、この日が制定された理由は、漢字の「鮭」の一部が「十一」の形に似ているからです。ここ数十年の間にサーモンは日本の回転寿司業界で絶大な人気を誇り、マルハニチロの調査によると、14年連続で消費者が選ぶ人気メニューの首位となっています。
サーモンが日本に広まったきっかけは、1980年代にノルウェーからの養殖サーモンが輸入されたことです。当時、回転寿司に登場することでその美味しさが一般に知られるようになりました。ノルウェーでは1960年代末からサーモンの養殖が始まり、1970年代には日本の市場に目を向けるようになりました。この動きが「プロジェクト・ジャパン」として展開され、試食会や寿司職人へのプロモーションを通じて、ノルウェー産のサーモンの市場が開かれたのです。
その結果、サーモンは子供から大人まで幅広い年代に人気となり、今や日本の消費量の約85%は海外からの輸入品に依存しています。日本各地でも養殖サーモンの生産が活発になり、三陸や九州、瀬戸内海でも高品質なサーモンが育てられています。近年では水温や養殖の条件を人工的に管理できる「陸上養殖」も注目されています。これは、養殖環境を最適化することで非沿岸地でも養殖が可能になり、持続可能な水産業への道を開いています。
特に目を引くのは、地域特性を活かしたブランドサーモンの誕生です。青森県の「海峡サーモン」、兵庫県の「神戸元気サーモン」、栃木県の「うつのみやストロベリーサーモン」など、各地で特色あるサーモンが育てられています。また、近年では調味料や特産物を使用した新しい試みも進められ、「みかんサーモン」や「ふくいサーモン」などが消費者の注目を集めています。
回転寿司に欠かせないサーモンの魅力を深めるため、ノルウェーの水産業専門家へのインタビューを通じて、ビジネスの背景や未来の展望を探ります。また、くら寿司が行う地域サーモンの共同生産についても触れ、北海道の古清商店との「函館サーモン」プロジェクトや、愛媛県の「みかんサーモン」に関する開発秘話を明かします。
最後に、家庭で楽しめるサーモンのレシピも紹介。サーモンを題材にしたタルタルやソテーの作り方を通じて、地元産の鮭の日をお祝いするアイデアを提案します。毎年の11月11日を鮭の日として祝いつつ、サーモンの魅力を再確認する絶好の機会となるでしょう。私たちの食卓に彩りを添えるサーモンに、ぜひ目を向けてみてはいかがでしょうか。










サーモンが日本に広まったきっかけは、1980年代にノルウェーからの養殖サーモンが輸入されたことです。当時、回転寿司に登場することでその美味しさが一般に知られるようになりました。ノルウェーでは1960年代末からサーモンの養殖が始まり、1970年代には日本の市場に目を向けるようになりました。この動きが「プロジェクト・ジャパン」として展開され、試食会や寿司職人へのプロモーションを通じて、ノルウェー産のサーモンの市場が開かれたのです。
その結果、サーモンは子供から大人まで幅広い年代に人気となり、今や日本の消費量の約85%は海外からの輸入品に依存しています。日本各地でも養殖サーモンの生産が活発になり、三陸や九州、瀬戸内海でも高品質なサーモンが育てられています。近年では水温や養殖の条件を人工的に管理できる「陸上養殖」も注目されています。これは、養殖環境を最適化することで非沿岸地でも養殖が可能になり、持続可能な水産業への道を開いています。
特に目を引くのは、地域特性を活かしたブランドサーモンの誕生です。青森県の「海峡サーモン」、兵庫県の「神戸元気サーモン」、栃木県の「うつのみやストロベリーサーモン」など、各地で特色あるサーモンが育てられています。また、近年では調味料や特産物を使用した新しい試みも進められ、「みかんサーモン」や「ふくいサーモン」などが消費者の注目を集めています。
回転寿司に欠かせないサーモンの魅力を深めるため、ノルウェーの水産業専門家へのインタビューを通じて、ビジネスの背景や未来の展望を探ります。また、くら寿司が行う地域サーモンの共同生産についても触れ、北海道の古清商店との「函館サーモン」プロジェクトや、愛媛県の「みかんサーモン」に関する開発秘話を明かします。
最後に、家庭で楽しめるサーモンのレシピも紹介。サーモンを題材にしたタルタルやソテーの作り方を通じて、地元産の鮭の日をお祝いするアイデアを提案します。毎年の11月11日を鮭の日として祝いつつ、サーモンの魅力を再確認する絶好の機会となるでしょう。私たちの食卓に彩りを添えるサーモンに、ぜひ目を向けてみてはいかがでしょうか。










トピックス(グルメ)
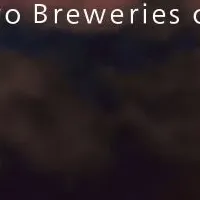






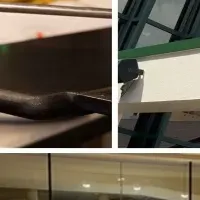
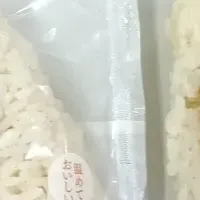

【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。