
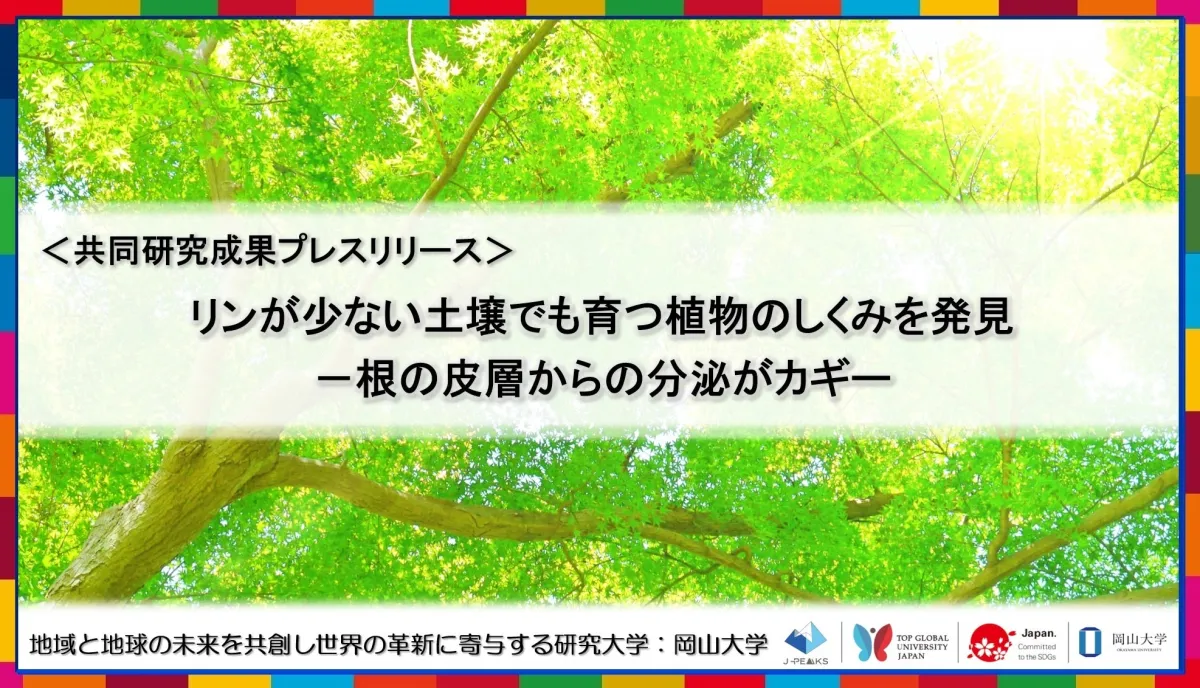
新たに発見されたリンが少ない土壌で育つ植物の秘密とは?
ポイント
広島大学、岡山大学、北海道大学、山形大学の研究チームは、超低リン耐性植物がその特殊な根の構造を持つ理由を解明しました。この植物は、リンが少ない土壌でも元気に育つため、農業や環境保護において重要な存在となり得ます。
超低リン耐性植物の特性
超低リン耐性植物とは、土壌中のリンが少ない環境でも成長が可能な植物を指します。これらの植物は、リンを効率的に吸収するための特殊な根の構造を持っています。特に、南西オーストラリアに自生するピンクッションハケア(Hakea laurina)は、その代表例として知られています。
この植物は、通常の根と比べて細かい側根が密集した「クラスター根」を形成しており、根の表面積が大きくなるため、より多くのリンを吸収することができます。さらに、このクラスター根は多量の有機酸や酸性ホスファターゼを分泌し、土壌中のリンを吸収しやすい形に変えることができるのです。
分泌のメカニズム
これまでの研究では、根の表皮から分泌物が放出されると考えられていましたが、本研究により、クラスター根の「皮層組織」がその主な役割を果たしていることが明らかになりました。具体的には、リンゴ酸トランスポーター遺伝子HalALMT1がこのプロセスに関与していると考えられています。
研究チームは、根の皮層からの分泌物がスムーズに根圏土壌中に拡散される仕組みを解明しました。これは、超低リン耐性植物が特有のスベリン外皮を形成しないため、他の植物と比べて根分泌能力が高まることに由来しています。この発見により、クラスター根のリン獲得能力を作物に応用する可能性が期待されます。
研究の意義
今回の研究は、クラスター根の特異な特徴を解明することで、農業における作物の栽培や、環境における土壌改良に役立つ知見を提供します。また、食糧不足や土壌の劣化が問題視される現代において、超低リン耐性植物の利用が求められる背景があります。
この研究発表は2025年5月27日に行われ、論文は『New Phytologist』に掲載されています。この成果を活かすことで、持続可能な農業の発展が期待され、多くの国や地域での農作物生産の向上に寄与するでしょう。
さらに、広島大学をはじめとする研究機関の共同研究は、地域社会や地球全体の持続可能な発展にも貢献することが期待されます。今後のさらなる研究や応用に注目が集まっています。
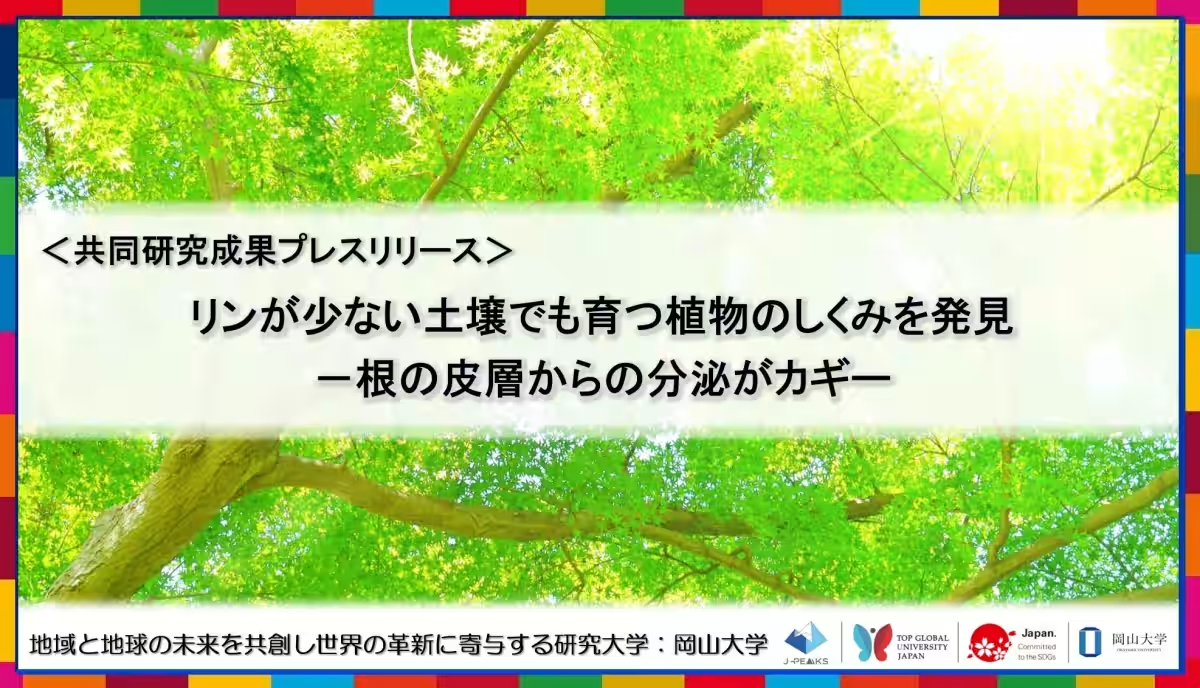



関連リンク
サードペディア百科事典: ピンクッションハケア 超低リン耐性植物 根の分泌
トピックス(その他)


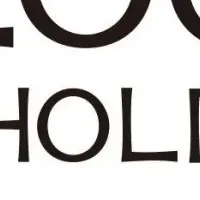

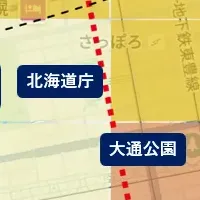
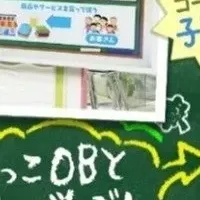


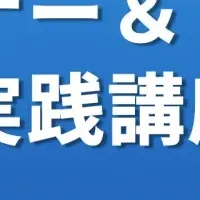
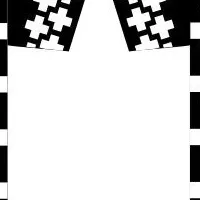
【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。