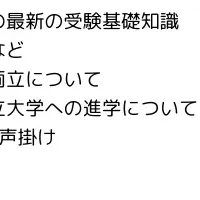
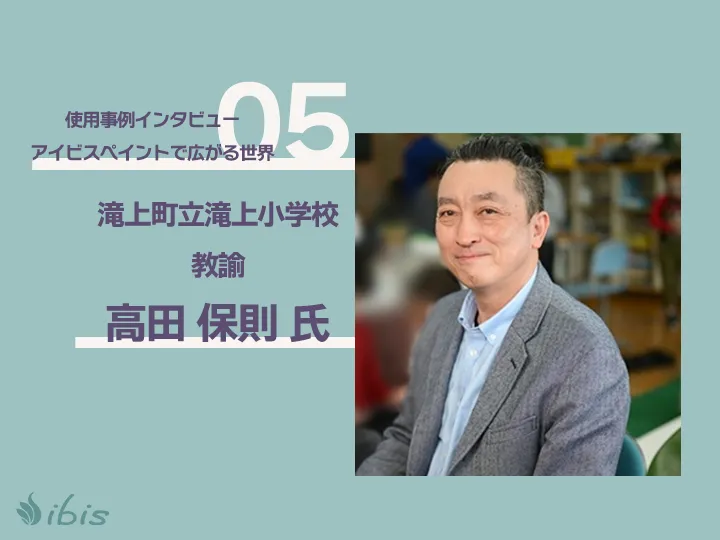
北海道の小学生が学ぶネットリテラシーの創造的アプローチ
北海道の小学生が学ぶネットリテラシーの創造的アプローチ
北海道の滝上町立滝上小学校で行われたネットリテラシー教育が注目を集めています。教諭の高田保則先生が紋別市立紋別小学校に所属していた時に実施したこの取り組みは、モバイルペイントアプリ「ibisPaint」を活用し、SNSの疑似体験により、子どもたちが情報モラルを実践的に学ぶ場を提供しました。
特に、「ibisPaint倶楽部」と名付けられたオンラインコミュニティでは、子どもたちが自由に描いたイラストを投稿し、コメントを交わし合うことで、クリエイティブな交流を促進しました。この活動は、情報端末を子どもたちに提供することから始まり、子どもたちは自分の作品を共有することで,他者との関わり方を自然に学んでいったのです。
「ibisPaint倶楽部」の活動内容
高田先生によると、「ibisPaint倶楽部」は、Googleクラスルームを基盤にしたコミュニティであり、イラストを気軽に投稿し合う場として設計されていました。年間200件を超える作品が投稿され、日常的に活発な交流が行われました。特に夏休みには、多くの子どもたちがデジタルアートに熱中し、創造的な時間を過ごす姿も見られました。
そんな中で、低学年の子どもが高学年の子どもから技術的なアドバイスを受けたり、仲間同士で励まし合う姿も垣間見ることができ、参加者全体のコミュニケーション力が向上していることが証明されました。高田先生は、このような環境が子どもたちの表現力を育む上でどれほど重要であるかを実感していました。
情報モラルの教育的意義
高田先生は、ネットリテラシー教育について意義深い見解を持っています。従来のリスク中心のアプローチではなく、子どもたちがコミュニケーション能力を磨き、ポジティブな関係を築くことが重要だと考えています。「ibisPaint倶楽部」は、まさにその安全な疑似SNSとして機能し、より良いオンラインコミュニティの形成を促進しました。
特に、コミュニケーションに必要なリスペクトや協力の重要性を体験することが、子どもたち自身の成長に大きく寄与しました。具体的なフィードバックを通じて、子どもたちはインターネットを安全に使用する方法を学び、成長していくことが期待されています。
高田先生の願い
高田先生は、子どもたちがネットやSNSを活用する未来に向けて、大人がしっかりと安全な環境を提供しながら、自由な表現を促す役割を果たすべきだと語ります。子どもたちには、自分の興味や情熱を存分に追求してほしいとの思いは強く、これが将来の自己実現に繋がると信じています。
教育者として、彼の取り組みは他の全国の教育現場にも良い影響をもたらすでしょう。「ibisPaint」がもたらす可能性は、単なるアプリ以上の価値を持っていることが垣間見えます。これからも、子どもたちの未来を見つめながら創造的な学びの場を広げていきたいという高田先生の情熱は、私たちにも大きなインスピレーションを与えています。
まとめ
このように、北海道の小学校での「ibisPaint倶楽部」の活動は、AIやデジタルアートの普及が進む現代社会において、子どもたちがどのようにしてネットリテラシーや情報モラルを学んでいるのかを示す一例です。高田先生の話を通じて、教育の新たな形や可能性を感じさせていただきました。今後も、このような取り組みが全国各地で進化を遂げることを期待しています。
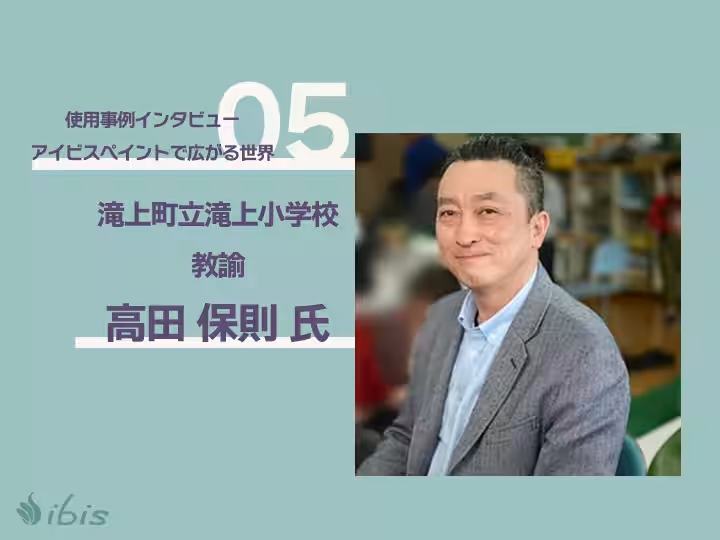






トピックス(習い事)
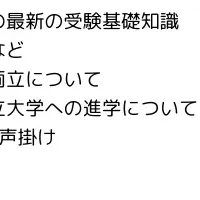




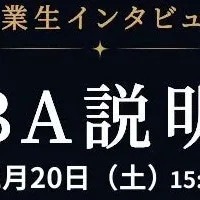

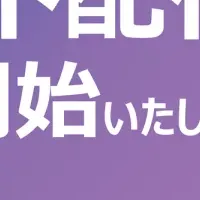
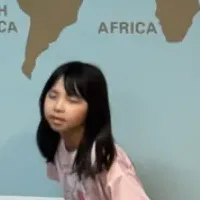
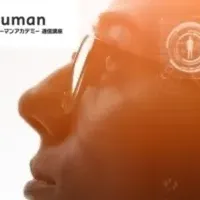
【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。