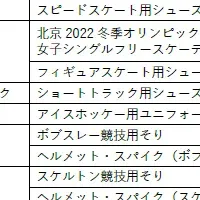

教育の未来を見据えた「ウェルビーイング」研究プロジェクト始動
教育の未来を見据えた「ウェルビーイング」研究プロジェクト始動
令和7年7月2日、国立大学法人東京学芸大学が中心となり、「教育ウェルビーイング研究開発プロジェクト」のキックオフミーティングがオンラインで行われました。本プロジェクトは、全国の5つの教育委員会や学校と連携し、児童や生徒、教職員が心身ともに健やかに学び働ける環境を目指しています。
プロジェクトの背景と目的
近年、ウェルビーイングは教育政策や国際的な教育指針において重要なテーマとなっています。OECDは、教員の専門性とウェルビーイングに焦点を当てた「Teaching Compass」を発表し、これにより教育現場でのウェルビーイングの可視化と活用が不可欠な取り組みと位置付けられています。本プロジェクトは、こうした国際的な潮流を受け、教育委員会との対話を通じて独自のウェルビーイング指標を共同で開発することを目指しています。
キックオフミーティングの詳細
当日は、東京学芸大学の學長、國分充氏の開会挨拶から始まり、プロジェクトリーダーの荻上健太郎准教授が趣旨を説明。その後、各教育委員会からの発表が行われ、各地域の教育ビジョンや課題について具体的に語られ、活発な意見交換も行われました。
登壇内容の一部
- - 中頓別町教育委員会 教育長 大島朗氏は、「人生100年学びの拠点・中頓別学園」プロジェクトの取り組みを紹介。地域全体を学びの場として、新しい時代の教育実践に向けた環境づくりを強調しました。
- - 大熊町教育委員会 教育長 佐藤由弘氏は、震災から復興を遂げる町でのウェルビーイングの意義について考えを述べ、子どもたちにとっての教育の役割を強調。
- - 葉山町教育委員会 教育長 稲垣一郎氏は、心の「ワクワク」を重要視し、小中一貫教育を進める中で非認知能力の向上を目指す取り組みを発表。
これらの発表は、各教育委員会が抱える課題や期待を明確にし、教育ウェルビーイングの重要性を改めて認識させるものでした。
未来を見据えた取り組み
本プロジェクトでは、教育界全体のウェルビーイングを定量的・定性的に測定・分析する取り組みが進められており、これにより教育の質や効果を継続的に把握する仕組みが構築されます。また、教育の担い手となる人材の育成にも力を入れており、将来の教育を支えるためのフィールドを整えることに注力しています。教育現場が直面する複雑な課題に対し、多角的なアプローチを通じた解決策の模索が行われることでしょう。
結論
教育の未来を担う「教育ウェルビーイング研究開発プロジェクト」は、地域の教育実践を向上させる重要な取り組みです。このプロジェクトが全国の教育現場にとって新たな指針となり、子どもたちや教育関係者のウェルビーイング向上に寄与することを期待しています。

トピックス(その他)
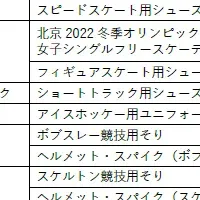



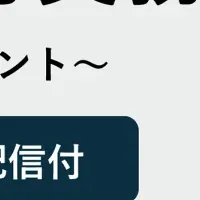
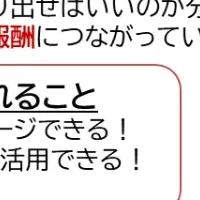



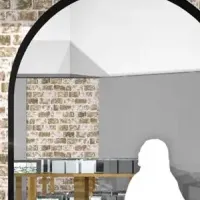
【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。